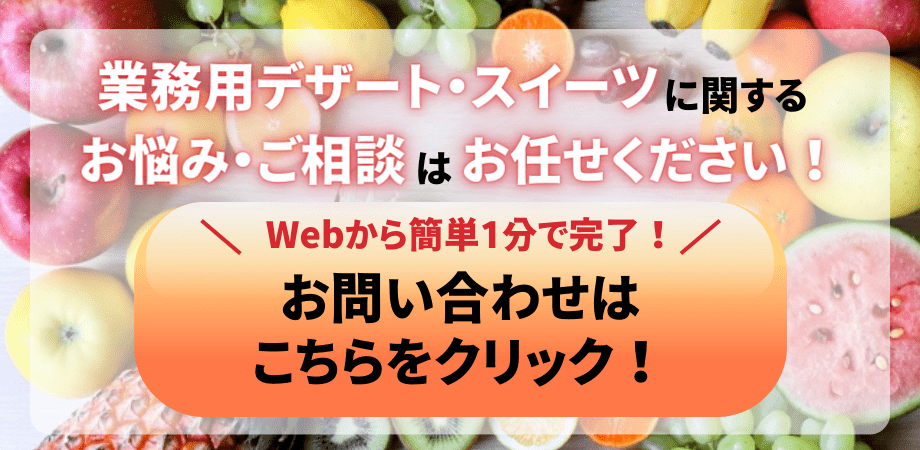介護や医療現場では、「きざみ食」という言葉をよく耳にします。加齢や病気によって食べ物を噛む力や飲み込む力が低下した方に対して提供される食事形態の一つです。しかし、メリットばかりが注目されがちで、実は「誤嚥」や「見た目・味の変化」などのデメリットも存在します。
今回のコラムでは、きざみ食の基礎知識からメリット・デメリット、さらに現場での運用上の注意点や代替え手段などを解説します。
きざみ食とは
きざみ食とは、食材を細かく刻むことで噛みやすくし、嚥下しやすくした食事形態のことを指します。対象となるのは、主に高齢者や、脳卒中後の後遺症、神経疾患などにより咀嚼・嚥下機能が低下した方です。
刻む大きさには段階があり、一般的に以下のように分類されることがあります。
・粗きざみ(大きめのみじん切り)
・中きざみ(5mm程度)
・極きざみ(ペースト状に近い)
きざむことで食べやすくなりますが、単純に「細かくすれば安心」とは限りません。食べ物の硬さ、調理の工夫やトロミの追加なども重要なポイントとなります。

きざみ食のメリット
噛む負担を軽減できる
きざみ食の最大の利点は、咀嚼の負担が軽減される点です。歯が少ない方や、入れ歯を使用していて硬いものが噛めない方でも、細かく刻むことで無理なく食事ができます。
食材の幅が広がる
通常の状態では提供しづらい食材(たとえば繊維質の多い野菜や肉類)も、刻むことで摂取可能になります。これにより栄養バランスを保ちやすくなります。
食欲低下を予防
ある程度の形が残っていることで、食材の彩りや味を楽しむことができ、食欲の維持にもつながります。ペースト食と比べ、食事らしさが残るという点で好まれる方もいます。
きざみ食のデメリット
誤嚥リスクが高まる
意外に思われるかもしれませんが、細かく刻むことで食材が口腔内に散らばりやすく、かえって飲みづらくなるケースがあります。バラバラになった食材が気管に入り、誤嚥性肺炎の原因になることもあります。
見た目や味の劣化
複数の食材を一緒に刻むと、料理全体が均一な見た目になりがちです。色や形の違いが失われ、「おいしそうに見えない」「味が混ざってしまう」といった声も多くあります。
栄養価が下がる場合も
刻んで加熱し直す過程で、水分や栄養素が流出することがあります。特に野菜類はその傾向が強く、見た目や味だけでなく栄養面の配慮も必要です。
現場での課題と注意点
介護施設や病院では、きざみ食の提供には人手と手間がかかります。刻む作業自体にも衛生管理の注意が必要で、食材ごとの硬さや水分量にも気を配らねばなりません。
また、きざみ食を「どの程度刻むべきか」「トロミを加えるべきか」は個々の嚥下レベルによって異なります。医師や言語聴覚士などの専門職との連携が不可欠です。
きざみ食の代替として注目される食事形態
ざみ食に代わる「ソフト食」「ムース食」「ミキサー食」といった食事形態も注目されています。
ソフト食
形ある程度残しつつ、舌や歯ぐきでつぶせる柔らかさが特徴。見た目が通常食に近く、食事の楽しみを損ないにくい。
ムース食
素材の味を生かしながら、ムース状に固めて提供する方法。見た目の再現性が高く、誤嚥リスクも軽減されます。
ミキサー食
ミキサーにかけた後、水分が多いのでとろみ剤などで、とろみをつけることで「飲み込みやすく」「食べやすい」形態に加工されたものが一般的です。
これらは専門的な調理技術や食材が必要になるため、導入コストと人材の確保が求められますが、誤嚥予防の観点から非常に有効です。
まとめ
きざみ食は、咀嚼や嚥下に困難を抱える方にとって、大きな助けとなる食事形態です。しかし、その効果を最大限に活かすためには、個々の利用者の状態に合わせた調整や、栄養・味・見た目のバランスにも配慮が必要です。
きざみ食が適切でない場合もあり、代替えとなる形態食や調理法を取り入れることで、より安全で満足度の高い食事の提供が可能になります。
食べること「生きる力」につながる大切な行為。高齢者や要介護者にとって、楽しく安心して食べられる環境づくりが、今後ますます求められていくでしょう。
また、「業務用デザート・業務用スイーツ.com」では、多くの栄養補助食品をご用意しております。無料サンプルもございますので、少しでも気になった点がある方は、下記よりお問い合わせください。