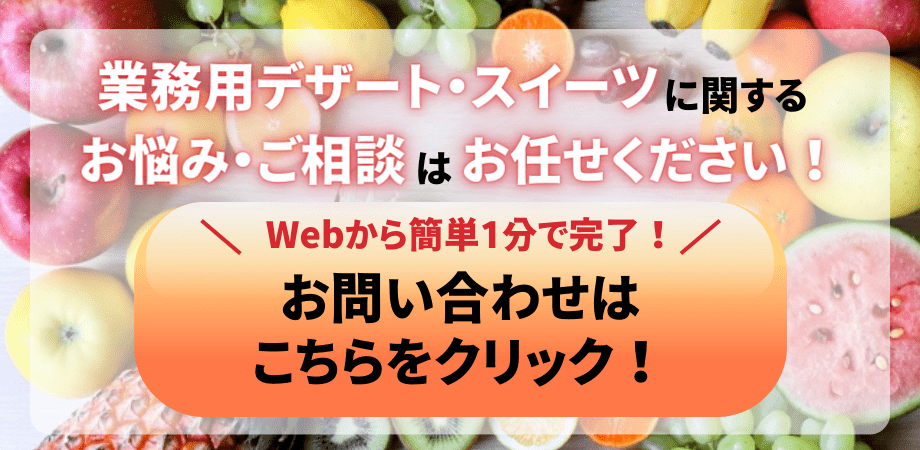「まごわやさしい」とは、健康的な和食を作るための栄養バランスの指標です。この7つの食材を意識することで、体に優しく、健康長寿にもつながる食生活を実現できます。そして、この言葉は、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで注目を集めています。
2013年12月「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されて来年で早10年となります。
そこで、もう一度、日本食(和食)の良さを再認識するとともに、和食の合言葉「まごわやさしい」を確認し、栄養バランスのよい食事のきっかけになればと思います。
日本食(和食)の良さとは?
ユネスコ無形文化遺産に登録された理由には大きく4つの要素があります。
・多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重
日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根差した多様な食材が用いられています。また、素材の味わいを生かす調理技術・調理道具が発達しています。
・ 健康的な食生活を支える栄養バランス
一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。
また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿や肥満防止に役立っています。
・自然の美しさや季節の移ろいの表現
食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節にあった調度品や器を利用して、季節感を楽しみます。
・正月などの年中行事と密接な関わり
日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」
を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。
和食はバランスが良い
和食の基本を形成するこの合言葉は、栄養バランスが良く、体に優しい食材をバランス良く摂取することを意味しています。日本は世界でも有数の長寿国で日本食(和食)が健康に寄与していることは明らかです。そして、一汁三菜を基本とした日本食のバランスの良さが世界的にも高く評価されています。その日本食(和食)のバランスで大事な合言葉が「まごわやさしい」です。
具体的には、豆、ゴマ、わかめ、野菜、魚、椎茸(きのこ類)、芋、の略が「まごわやさしい」です。
「まごわやさしい」それぞれの栄養価値は?

「まごわやさしい」の種類と、それぞれの栄養価値を書いてみました。
ま=まめ
まめ(落花生、大豆、枝豆、小豆、そら豆、いんげん豆、ひよこ豆、レンズ豆など)
良質なたんぱく質が豊富で、筋肉や皮膚、髪の健康をサポート。大豆イソフラボンには、ホルモンバランスを整え、更年期症状の軽減や骨粗しょう症予防の効果もあります。
ご=ごま
ごま(白ごま、黒ごま、金ごま、ねりごま、すりごま、ごま油、アーモンド、栗、ぎんなん、ピーナッツなど)
ごまに含まれるセサミンは、抗酸化作用があり、老化防止や肝機能向上に効果的です。また、不飽和脂肪酸が血流を改善し、動脈硬化予防に役立ちます。
わ=わかめ
わかめ(わかめ、昆布、ひじき、もずくなど)
ミネラル(カルシウム・マグネシウム)が豊富で、骨や歯を強くし、骨粗しょう症予防に貢献します。また、フコダインという成分が腸内環境を整え、免疫力アップに効果的と言われています。
や=やさい
野菜は、1日350gが目安です。(1/3は色の濃い野菜(緑黄色野菜)、2/3は淡色野菜)
ビタミンや食物繊維が豊富で、美肌効果、便秘解消、免疫力アップに効果的です。特に緑黄色野菜には抗酸化作用があります。
さ=さかな
さかな(あじ、いわし、あさり、さば、鮭、まぐろ、たこ、えび、牡蠣、しじみ)
特に青魚に含まれるDHAやEPAは、脳の働きを活性化させます。また、オメガ3脂肪酸が血液をサラサラにし、心疾患リスクを軽減します。
し=しいたけ
しいたけ(椎茸、舞茸、えのき、しめじ、エリンギ、なめこ、マッシュルーム)
しいたけを代表とする一般に「きのこ類」を表しています。きのこ類は、ビタミンDが豊富でカルシウムの吸収を助け、骨を強くします。また、食物繊維が腸内環境を整え、便秘解消や血糖値の上昇を抑える効果もある低カロリーでヘルシーな食材です。「菌活」という言葉も一時は使われる時がありました。
い=いも
いも(じゃがいも、さつま芋、里芋、長芋など)
じゃがいもやさつまいもには、ビタミンCが豊富で美肌効果や風邪予防にも役立ちます。食物繊維が多く、腸内環境を整え、便秘解消やデトックス効果も期待できます。揚げ物や煮物、味噌汁、おやつなど幅広く活用できる便利な食材です。
「まごわやさしい」を意識することで、普段の食材選びや献立にも変化があるかもしれません。
これらの食材を組み合わせることで、和食はその多様性と栄養のバランスの良さを実現しています。この「まごわやさしい」の原則に従って食事を構成することで、健康を維持し、病気の予防にもつながるとされています。和食の素晴らしさは、単に味だけでなく、栄養バランスや身体に良い影響をもたらす点にあります。そのため、和食は世界的にも注目を集めている食文化の一つと言えるでしょう。
【関連記事:健康的な食生活で知っておきたい!PFCバランスとは?】
和食は本当にいい事ばかりか?
実は和食にも問題点はあります。バランスのよい食事と言われておりますが、「カルシウムが少ない」「塩分の過剰摂取になりがち」と言われております。
カルシウムは、骨や歯の材料となるミネラルです。和食でもカルシウムを含む小魚や緑黄色野菜は使用しますが、乳製品と比べるとカルシウムの吸収率が悪いため、牛乳やチーズなどを積極的に取り入れましょう。
また、日本の水は軟水なので、海外の硬水と異なりカルシウムやマグネシウムなどのミネラルを含まない水のため、飲料水からはカルシウムを補えません。
塩分の過剰摂取について、和食は味噌や醤油など食塩を多く含む調味料を使用する事が多いです。昔から野菜や海藻類などの保存食として利用されていた梅干し、漬物、佃煮など食塩を多く含むものを食事に食べることにより、食塩の摂取量が多くなっております。
【関連記事:栄養バランスを考えて作ったアイスは、こちらをクリック】
まとめ
今までの食事から急に「まごわやさしい」を意識して作りましょう!とか、「毎食一汁三菜」にしましょう!というのは、実は簡単に出来るものではないと思います。ちょっと食事の献立を意識してみるところから始めるのがいいかもしれませんね。
最後に、この記事で紹介した内容を簡単にまとめておきましょう。
・日本食(和食)の良さとは
◎2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された4つの理由
・和食はバランスがよい
◎一汁三菜を基本として、「まごわやさしい」のバランスは世界的にも評価されている。
・「まごわやさしい」について
◎豆、ごま、わかめ、野菜、魚、椎茸(きのこ類)、芋について種類と栄養価値
・和食は本当にいい事ばかりか?
◎カルシウム不足、塩分過剰摂取に注意
また、「業務用デザート・業務用スイーツ.com」では、カルシウムを多く含んだデザートを含め、多くの栄養補助食品をご用意しております。無料サンプルもございますので、少しでも気になった点がある方は、下記よりお問い合わせください。